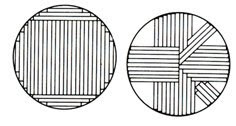アルヴァ・アアルトが、開発を続け
アアルト・レッグという
新たな成型合板の進化をとげている1950年代、
アメリカでは、チャールズ・イームズが
成型合板で、2方向以上の曲線を作り出そうとしていました。
ニクロム線の通った、石膏型に
接着剤を塗った合板を圧着させ、乾燥させる方法です。
この方法で生まれたのがこのチェア。
『DCW』です。
二次曲面をもつ脚と、三次曲面をもつ背・座からなっています。
一方、デンマークでは、
背から座まで一体成型された三次曲面のチェアが発表され、
世間を驚かせました。
建築家アルネ・ヤコブセンがデザインした
『アント(アリの事)チェア』です(1952年)。
日本では、『アリンコチェア』という愛称で
今でも、多くの人たちに愛されているチェアです。
軽くて、スタッキング(重ねること)が出来る椅子として
デザインされた物で、当時は3本脚でした。
連続した背と座の部分は、
9枚のベニヤを交差させながら、型に入れます。
そしてプレスして作るのですが、三次曲面にすると
腰の部分が割れてしまう為、削り取り、くびれた形になっています。
ヤコブセンの没後、安定感のある
4本脚の『アントチェア』も生まれました。
プレスの仕方や、木の乾燥の加減、単板層の重ね方などをさらに研究し、
これらの椅子を、現在までベストセラーとして育て上げた
「フリッツ・ハンセン社」は、
1915年に、いち早く曲木椅子の製造を始め、
研究を重ねていたのです。