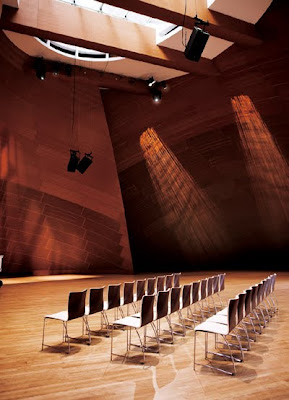今では、人口の半数近くがベッドを使用するようになりました。
住宅の洋風化がすすみ、ベッドの普及率が上がったのですね。
そんな、今では普通になりつつある日本のベッドの歴史は
今から85年前に始まります。
日本で始めてベッドを作り始めた会社「日本ベッド」のコーナーが
リニューアルしました♪
新しい商品も入りましたので、日本ベッドさんによる、説明会が開催されました。
日本ベッドは、一人ひとりの寝心地の好みに合わせられるよう
コイルの線形を5段階にも分けて、ポケットコイルを作り分けています。
また、そのコイルは耐久力を向上させる為
世界で初めて、熱処理を行なったそうです。
長く使うものだから、
冷却と同時に防錆処理も行なっています。
このおかげで、硬度と耐久性が30%もアップしたそうです!
注目は、ポケットコイルを従来型のポケットマットレスの
約2倍の1200個(Sサイズ)を組み込んだ超高密度構造「シルキーマット」
自社でスプリングマシーンを開発し、
他者に真似できない、世界で始めてのマットレスです。
ウォーターベッドの寝心地を、持ち運べるポケットコイルマットレスで実現。
より高級な寝心地を提供できる、マットレスです!
今回TERRAに展示されたのは、いずれも高品質で
(下の写真:シルキーポケットに高級縁取り2層仕上げのピロートップマットレス。
弾力性・復元力・耐久性にすぐれた100%ラテックス詰め物を使用しています。)
しかも、一人ひとりに合わせて
マットをお選びいただきやすいように、なっています♪
(硬さが選べる、シルキーマットレス、ビーズポケットマットレス。写真はビーズ)
硬さが選べるマットレス各種を
わかりやすく、展示していますよ。
さらに、フレームのオーダーも、できるんです!
ウッドのカラーも3色ご用意。
サイズをオーダーして、高級ホテルの寝心地とデザインを
ご自宅で堪能していただく事ができます。
ベッドマットをお選びの際は、腰かけるだけじゃなく
ぜひ、横になってください。
社員も、一つづつ横になり、寝心地を確かめています。
この、革張りフレームは、4色から選べます♪
寝心地もデザインも、きっとご満足いただける日本ベッドコーナーには、
ベッドのスペシャリストスタッフがおりますので、お気軽にご相談くださいね。