こんにちは!
今日は2月29日ですね。
そう、4年に1度しかない日。
つい、何か残したくて、ネタも揃っていないのに
ブログを書き始めてしまいました。
2月29日が、どんな日なのか調べてみました。
インテリアや家具には、あまり関係の無い日のようです orz
にんにくの日らしいのですが、4年に1度しか訪れないなんて
残念ですね。
仕方が無いので(^^;)最近の社内のブーム。
女子社員の中で、ダイエットが流行ってきました。

こんにちは!
今日は2月29日ですね。
そう、4年に1度しかない日。
つい、何か残したくて、ネタも揃っていないのに
ブログを書き始めてしまいました。
2月29日が、どんな日なのか調べてみました。
インテリアや家具には、あまり関係の無い日のようです orz
にんにくの日らしいのですが、4年に1度しか訪れないなんて
残念ですね。
仕方が無いので(^^;)最近の社内のブーム。
女子社員の中で、ダイエットが流行ってきました。
先日、東京都立産業貿易センター「台東館」で開催いたしました
札幌ファニシング株式会社 「Spring Fair」には
たくさんのご来場誠にありがとうございました。
この場をおかりして、厚く御礼申し上げます。
会場では、SFオリジナルインポート新作発表や
北海道家具新作、大川新作、中部メーカー新作発表など
バラエティーも豊かに、あらゆるアイテムを展示・販売いたしました。
お得意先様におきましては、展示内容やその他ご要望などがございましたら
担当営業マンまで、お気軽にお申し付けください。
今後の催事に取り入れ、反映させていきたいと思っております。
最後に、会場の様子をビデオクリップにまとめましたので
ぜひ、ご覧くださいませ。
※音が出ます。
家族でゆったりとくつろげる、ゆとりのソファ
札幌ファニシングオリジナル家具
Neo Design 『SANTI -サンティ-』
職人さんに、
「妥協をゆるさず、リッチに、こだわって作ってください。」
と、お願いして作ってもらった、究極のソファです。
クッション部分に使われているのが
特殊な高比重ウレタン。
バネのような高い反発性は、汎用ウレタンの1.5倍以上。
そして、耐久性。繰り返し圧縮残留歪は、汎用ウレタンの1/5以下。
脚部は、四方に木を渡し贅沢なデザインに。
もちろん布張りはカバーリング対応。
60種類ものファブリックから、お好きな張り地をお選びいただけます。
革張りも対応いたします。こちらは良質の革9色をご用意。
TERRA5階でご覧いただけます。
ぜひ、リッチな座り心地をお楽しみください。
まだちゃぶ台の生活で、椅子など見たことも無かった時代に
洋家具を作るという決断は、革新的な出来事だった。
永年の経験と木の知識に支えられながら
「飛騨の匠」の技を受け継いだ職人たちの存在と
その挑戦を実現できるという自信が、
飛騨の洋家具作りを発展させていった。
昭和40年以降、日本人のライフスタイルは様式へと移行。
飛騨の家具メーカーも国内向けの商品開発に挑むと共に
飛騨デザインの確立を目指してきた。
・・・:::::::・・・:::::::::・・・:::::::・・・:::::::・・・:::::::::・・・::::
そうして作られたのが、飛騨デザイン憲章です。
飛騨の家具には、曲げ木やホゾ木といった
複雑で難易度の高い技術で作られています。
こうした木工の深い技術を生かしつつ、古い伝統の形を押し付けるのではなく
姿や表情を時代に合わせながら飛騨デザインを育てています。
そして、日本国内のみならず、海外の国際家具見本市でも
飛騨の家具は高い技術を認められ、高い評価を得ています。
※日本デザイン 世界へ発信
札幌ファニシングTERRAにも、この匠の技が光る
飛騨の家具を展示しています。
現在「飛騨の家具展」開催中。
ぜひこの機会に、匠の技にふれてみてください。
参考文献:新・飛騨の匠ものがたり
参考サイト:飛騨の家具・飛騨デザインの総合サイト
洋家具作りが始まったのは、大正9年である。
大正時代の飛騨は、鉄道もなく陸の孤島と呼ばれるにふさわしい
交通不便な山の中の町だった。
四方にそびえ立つ山々には、ブナの原生林がうっそうと繁り
昼も暗い密林地帯であった。
明治初期頃より、指物や箪笥などの和家具作りはされていたものの
当時、ブナ材といえば雑炭か下駄の歯程度の用途しかなく
無用の長物として見捨てられていた。
●飛騨の家具作りの発祥 ブナ材の曲げ木活用●
木材を蒸して型に入れ曲げる方法を世界で最初に考え出したのは
ドイツのミヒャエル・トーネットである。
1856年にオーストリアで世界で始めて曲げ木工場の建設に着手。
1859年には曲げ木椅子の多量生産を開始。
世界各国に販売され、今でも曲げ木といえばトーネット、
といわれるほどの椅子も生まれた。
その椅子の秘密は、ブナの木をUの字に曲げて椅子の部材を作る。
軽くて、輸送や製造コストも安くつく。
木理が通っているので、細くても丈夫。
たとえ壊れてもパーツの交換で修理が済む、というシンプルな基本構造にあった。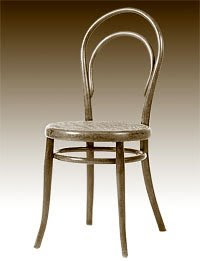
明治40年頃には、東京曲木や大坂の泉製作所が曲木家具の製作を始めた。
わが国における曲げ木家具製作の始まりである。
役に立たないとされていたブナの木が適材としての評価を得ると
ブナ材を求めて、明治44年には、秋田木工に、
9年後の大正9年には飛騨に伝わった、というわけである。
つづく
参考文献:新・飛騨の匠ものがたり
札幌ファニシングTERRA
「飛騨の家具展」開催中