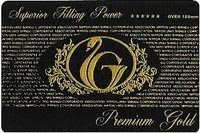明日は、2月10日。
そのゴロから、「ふとんの日」と呼ばれています。
そこで、今日と明日で
「羽毛布団と選び方」について
お話したいと思います。
まず、通常羽毛布団と呼ばれているものの
中身のお話から。
●ダウンと、スモールフェザー ********************************
ダウンとは、鳥のむねのあたりの、ふわふわの毛です。
鳥の種類、成長によって、大きさが違います。
スモールフェザーは、羽の形をしたごく小さいもの。
芯がありますが、小さいので、かたくはありません。
この、ダウンとフェザーの割合が、布団には表記されております。
ダウン率が50%を割ると、羽毛布団と呼べなくなり、
ハネ布団と呼ばれます。
ダウンは、その丸いカタチの通り、ダウンボールとも呼ばれ
寒い時には、広がり、
あたたかい時には、縮み、空気の流れを調節します。
ダウンボールが大きい物ほど、
その機能も有効で、高品質とされます。
この作用のおかげで、鳥も、私たちも
快適な温度を保てるんですね♪
●ダックと、グース *****************************************
ダックは、アヒル。
グースは、ガチョウ。
前を歩く、小さい方がダック:アヒル。
後の大きい方が、グース:ガチョウです。
ダック:アヒルは、ほとんどが食用のために育てられ、
若いうちに、精肉されます。
その時の、副産物として、羽毛が採取されます。
若いうちの羽なので、成長しきっておらず、小さいのです。
そもそも、グース:ガチョウの方が、アヒルより大きいので、
ダウンボールも大きくなります。
グースも、食用のものは、
アヒルと同じく若いうちに、採取される事になります。
同じグースでも、卵を産む事を目的に
しっかり成熟するまで育てられるのが、マザーグース。
このマザーグースのダウンボールが、
成熟して一番大きく、良いものとされています。
また、グース、ダック共に
シルバー種とホワイト種があります。
ホワイト種のほうが、人気のようです。
グースという記載が無い場合、
ダックの羽毛を使っています。
●鳥の出身地 **********************************************
羽毛布団の、羽毛は主に中国、ハンガリー、ポーランドなどから
輸入されます。
品質的には、やはり、ハンガリー、ポーランド等の
ヨーローッパ製をオススメします。
そして、寒冷地ほど羽毛が発達するため、
寒い国で育った方が、高品質と言えるでしょう。
ダウンボールの大きさや、その毛の量が品質の違いです。
この、品質の差は、「かさ高」を調べると、確かめられます。
かさ高とは:
30グラムの羽毛を、筒状の計測器にいれて
規定のおもりを、のせます。
一定時間の後、底から何㎜の厚さになっているか、を測り
平均値を、その羽毛のかさ高といいます。
その数値は、商品に表示されています。
その数値が高いものほど、高品質と言えます。
日本羽毛寝具製造共同組合に、その品質を認められたものには
ゴールドマークが、記されます。
・ニューゴールドラベル
かさ高120mm以上のもの
ラベルも、品質を見極めるヒントになると思います。
かさ高は、ダウンよりフェザーの方が大きいので、
ダウン率も同時に、確認しましょう。
羽毛布団を選ぶときには、
鳥の種類、原産地、ダウン率、かさ高を
総合的に、評価してみましょう。
明日は、羽毛布団の加工方法から見た
羽毛布団の選び方について、お話します。